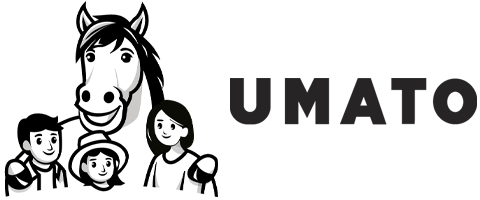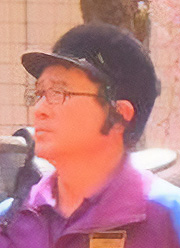牧場から初めてトレセンに入厩する2〜3歳の新馬は、まずトレセンのすぐ外にある検疫施設に入る。
厩務員(持ち乗り調教助手)がもらえる担当馬の賞金の一部(進上金)が全額プール制になっている厩舎を除き、ほとんどがその新馬を担当する人が、検疫に馬を引き取りに行く。
検疫に同じ厩舎の新馬が複数入る場合、誰がどの馬を担当するかは、厩舎のホワイトボードに書かれるか、本人に口頭で言われる。
大袈裟に言うと、その瞬間から僕たちとその馬の歴史が始まり、人生が大きく変わったりもするのだ。

僕は昔もごく最近も、自分の厩舎にその年どんな新馬が入るか調べた事がない。
今の矢作厩舎のようにドラフト制度などがあれば別だが、自分が担当するのが決まってから馬を初めて知りたいし、何も知らないほうが血統を含めた第一印象のドキドキや楽しみがあるからだ。
「誰があの高馬(高額で取引された馬など)やるんやろう…またあいつか!」といった厩舎の人間関係のドロドロにも参加したくないというのもあった。
検疫に行くと、血統の良い馬が入る上位厩舎とそうではない下位厩舎の人達のテンションの違いはハッキリ分かる。
「俺のは聞いた事ない血統で安い馬や」などと言って劣等感の塊になっている人もいるが、そういう値段の差をひっくり返すのもこの世界の面白さだと僕は思う。

こんな話を書いたのは、僕がトレセンに入って、第一印象で「この馬は凄いぞ…クラシックへ行けるかも?」と、初めて思った担当馬の話をしたいからだ。
オータムホーク ( 牡、父 シーホーク 母 ポートアイドル 1989〜1991年 伊藤雄二厩舎在籍 )

1989年の秋、この馬は僕の所にやってきた。
この馬社会に入って5年、喜びも悲しみも味わい、自分なりに着実に成果を上げてきた頃だったが、名の知れたランキング上位の種牡馬の新馬を担当するのは初めてだった。
シーホークは、晩年にさしかかったとはいえ、数年前には2年連続のダービー馬(ウィナーズサークル、アイネスフウジン)を輩出していた。
検疫で見た瞬間もビビッときたのだが、柔らかく大きな歩きと力強い調教を見て「この馬は大物になる!」と確信した。
デビュー戦は1990年のお正月競馬と決まったが、その3週間前くらいに脚に感染症(フレグモーネ)を発症し、3日ほど調教ができなかった。
今だから言えるが、この直前のアクシデントをふまえて伊藤雄二先生が「初戦はまだまだ7〜8分やな」と、記者やトラックマン達に言ったのでそこまで人気にはならなかった。
もちろん先生に聞いた訳ではないが、先生と仲の良い伊藤雄二厩舎番のトラックマンとかには、「この馬相当走るぞ」と常に言っていたので、儲けさせてあげようと思っていたのかもしれない。
僕は43年の厩務員人生で担当馬が「絶対勝てる!」と思ったのはたった2回だけ。
そのうちの1回がこのレースだった。
もちろん相手がある程度分かってからだが、この馬の底知れぬ能力に「この辺で負ける馬でない」と思い、僕も先生と同じく、番記者達に聞かれた時はそれとなく吹聴していた。
デビュー戦というのは、新聞などで人気のない馬は「もしかしたら…」と期待し、本命とかの馬は心配と不安ばかりになる。
オータムホークはそんな経緯があったし、偉そうに「負けるわけない」とか言ってしまったので、レース前からかなり緊張してしまい「惨敗したらどないしよ…」と、不安の塊になってしまった。
鞍上はまだデビュー3年目だった武豊騎手。
レースはオータムホークが2番手を追走、4コーナー手前から先頭に立ち、そのまま押し切り1着でゴール!
着差は1馬身半だったが、最後は手綱を緩めたので完勝と言える内容だった。

帰ってきた武豊騎手は「手応えも良かったし、上を目指せる馬です」と言った後、「あのー、このタテガミのダンゴは掴みにくくて、少し不安になります」と僕にそっとつぶやいた。
僕は入った頃からタテガミのオシャレに、3本に束ねた毛糸を編み込む「ワタリ」や、前回紹介したレゲエの三つ編みなどを駆使していたが、このレースで馬術の試合などでやっている「ダンゴ編み込み」に初めて挑戦したのだ。
現在なら馬の首に巻く「ネックストラップ」があるが、昔は無かったので騎手は馬が突然躓いた時などには、とっさにタテガミをつかんでいた。
それがこのダンゴだと掴みづらいとのことだった。

43年間、馬のタテガミに色々な編み込みをしてきた僕だが、武豊騎手にダメ出しを食らったこの馬術用のダンゴ編み込みは、この1回のみでもう二度とやらなかった。
そんな数々の思い出のある、オータムホークの新馬デビュー戦は無事勝利で終ったが、嬉しさより勝ててホッとしたという初めての感覚だった。
そしてこの馬は、僕にまた大きな喜びと悲しみをもたらす事になる…
つづく