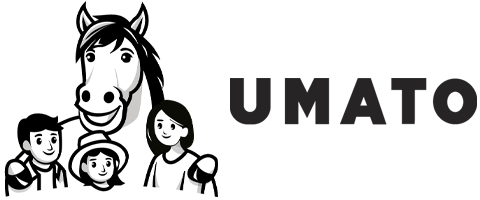初戦を快勝したオータムホークだったが、能力の高い大型馬の宿命ともいうべき調教の難しさに悩まされるようになる。
一完歩がとても大きく、乗り手の感覚がおかしくなるみたいで、普通の調教でもどんどんスピードが上がって止まらなくなり、制御不能になる事もしばしばだった。
もう栗東に坂路コースはあったが(まだ距離は500m)、余計に力んで走ってあまり効果はなかった。
勝てば皐月賞という若駒ステークスと、その次の1勝クラスは、最後方からのレースになり差し届かずともに5着。
前に行くとガーッと行ってしまいそうだったので、後方の内々を周る作戦にして失敗したようだ。
そして4戦目となった阪神競馬場でのはなみずき賞(現1勝クラス)。
思い切って先行し、4角先頭というデビュー戦以来の戦法で、9馬身差をつけて圧勝!
武豊騎手も「今回は折り合いもついたし、距離も長ければ長いほどよさそうです。」と、これからの出世に太鼓判を押してくれた。


レース後すぐの時点では、当時22頭フルゲートのダービーの抽選に賭けるか、ダービートライアルに行くか?という話も出ていた。
しかし次の日に脚をチェックしたら、少し腫れが見られたので、伊藤先生にすぐ報告すると「先のある馬なので、いわき温泉で休ませよう」と即断。
それは競走馬の致命傷でもある「屈腱炎」の兆候だった。
当時のエコー検査は今ほど精密ではなく、競走馬診療所では屈腱炎の初期段階という診断で、温泉治療すれば完治するかも?という判断での処置となった。
オータムホーク1頭だけ馬運車に乗せて、僕は初めて行く福島県のいわき温泉(常磐支所、現競走馬リハビリテーション)にトンボ帰りで連れて行ったのを思い出す。
秋の菊花賞路線には間に合わず、再起はその年の12月になったが、成績は期待外れ。
脚元が気になっていたからか、強い調教不足でかなり太めの体重で出走し、あまり良いパフォーマンスができないレースが続いた。
月イチペースでレースを使ったオータムホークは、体重が絞れてくるとその能力の高さを発揮するようになり、2着が続いた後の1991年4月の中山2勝クラス特別を快勝。
ようやく本格化かと思われたが、一度屈腱炎の診断をされた馬には常に再発の危険がつきまとう。
僕は毎レース悪い意味でドキドキし、次の日の脚チェックまで気が気ではなかった。
勝っても心の底から喜んでいなかったと思う。
そして常に持っていたその悪い予感は、現実のものとなってしまう。
1991年5月12日、東京競馬場。
この日は10R安田記念(G1)に僚馬ダイイチルビーが出走。
その前の9R緑風ステークス(現3勝クラス)にオータムホークは断然の1番人気で出走した。
中団を落ち着いて追走し、3コーナーあたりからジワジワ上がっていったが、直線に入って思ったほどの伸びはなく4着でゴール。
柴田政人騎手が「走ってる時はどうもなかったけど、止める時、変な感じだった」と一言。
スタッフは安田記念のパドックに急いだので、僕一人でレース後の目洗いの為に義務付けられている診療所へと向かった。
たしかに歩様は悪かった。診療所に着いて目洗いしながら脚元を診てもらった。
獣医さんが「前脚の両方とも屈腱が断裂してるようです」と一言。
すぐ僕も前脚の腱を触ったら、腱と言えるしっかりした部分は全くなく、すべて水風船のようにプニョプニョして腫れていた。
そしてこの時点から歩くのもままならなくなった。
「両前が断裂したのでここまで惰性で歩いて来れたのでしょう。片方だけなら多分歩けてません。」
「改めての診断になりますが、能失(競走能力喪失)でしょう。」
涙が溢れてきたが「先生、能失だと命は助かるんですか?」と聞くと、
「時間はかなりかかりますが、歩けるようにはなると思います。」と返ってきた。
「助けてやって下さい、よろしくお願いします!」
そんなやりとりをしながら湿布で両前脚をぐるぐる巻きに固定してもらっている時、ダイイチルビーが安田記念を勝ったと獣医さんから知らされた。
処置が終わり、厩舎に馬運車で帰ってしばらくすると、ダイイチルビーと担当の大當(おおとう)末彦厩務員が帰ってきた。
涙が枯れるほど泣いた後だったので、涙の跡を洗ってから心を落ち着けて、声を振り絞り「おめでとうございます!」と大當さんに言った。
僕はこの時こう思っていた。
獣医さんが言った「両脚が断裂したから惰性で帰ってこれた」は違う。
とてつもない痛みと恐怖を助けてくれるのは僕だと思って、僕の所に必死に帰ってきたのだ。

その後、正式に能失という診断結果となり、しばらく栗東で休ませたが、馬運車に乗せて長距離を走っても大丈夫となり、どこかへと旅立っていった。
「厩舎を去った馬を追いかけてはいけない」と、いつも先輩に言われていた。悲しい現実を知る事が多いからだ。
だからこの後の消息は分からない。 「痛かったな……ごめんな……夢をいっぱい見させてくれてありがとう。」
そうつぶやきながら、オータムホークを乗せた馬運車を涙で見送った。