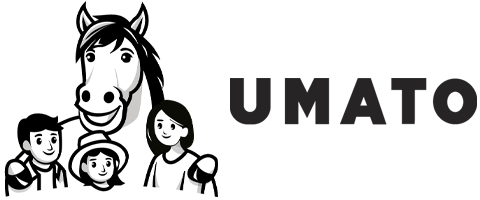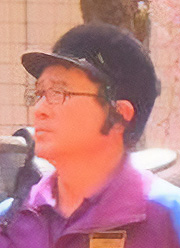厩務員や持ち乗り調教助手の1頭の馬の入厩から放牧までの担当期間というのは、時代でかなり違うし、調教師(厩舎)やオーナーサイドの方針で厩舎によっても大きく違う。
現在は栗東トレセンや美浦トレセンから程近い場所に育成(トレーニング)牧場があり、活発に放牧〜入厩が繰り返されている。
トレセン入厩から10日経たないとレースに出走する事ができないが、牧場で乗り込んでいるので、2週間前後でレースに使うのも今では珍しくない。
どこの厩舎も1頭のトレセン滞在期間は長くても3ヶ月くらいで、レース出走も3回〜5回くらいだろう。
でも昭和の時代は、放牧という概念は大きな怪我や疾病以外ではあまりなく、担当馬が1年以上トレセン厩舎にいるのは普通だった。
僕が入った頃は、ようやく放牧の重要性が分かってきて、伊藤雄二先生も少しでもトレセンから近い育成牧場を探して放牧地として利用していた。
でも牧場の馬房枠やタイミングもあり、ずっと厩舎にいる馬もまだかなりいて、デビューから抹消まで放牧なしも少なからずあった。
そんな馬の1頭が、マチカネハナノエンだ。
初入厩から抹消まで約2年間、一度も放牧に出る事なく僕が担当していた。
現在は1年の半分は放牧に行っている感じなので、今の4年分くらいの付き合いになるかな?

当時は、全休日の月曜日も朝や夕方に厩舎に顔を出していたので、2年間ほぼ毎日顔を見ていたハナちゃん。
性格は温厚で人懐っこく従順。運動や調教も特に困る事もなく敷料も汚さず、厩務員としては最高の馬だった。
彼女の得意技は「チャック上げ下げ」。
今で言うとファスナーとかジッパーだが、あえて当時の昔言葉のチャックと言わせてもらう。
ジャンパーやカバンなどチャックのあるものを察知すると、咥えて動かすのだ。上下や左右、何度でも往復する。
「これは使える!」と思った僕は、やる度に人参を与えて褒めた。
すると必死にチャックを探すようになり、僕以外のお客さんの物でも上下に動かすようになった。
ハナちゃんは僕が作り上げた、芸馬?第1号だ。
成績も安定してきたが、平地競走で未勝利と1勝クラスを2連勝した後、2勝クラスでは少し頭打ちするようになる。
でもレース後すぐ息が入りケロッとしている心肺機能の良さから、「長距離や障害とかいけるかも?」みたいな話になり、障害練習をしてみる事になった。
障害練習は基本、レースでも乗ってもらう騎手に頼む。
ハナちゃんは林満明騎手に依頼したが「いやぁ、これはモノになりますよ、飛びもうまいし。」と絶賛。
しばらく障害練習をしてから試験を受け、見事1発合格。
障害デビュー戦こそ後手を踏んだハナちゃんだったが、その後6戦2勝し、2着2回、3着2回という素晴らしい成績を残した。






しかしオープン昇級初戦で、初めて落馬してしまった。
障害コースの中で東京競馬場は大回りで広いので、いつもよりスピードが上がり、ジャンプするタイミングが早くなってしまったのが原因らしい。
その後、ハナちゃんは障害を飛ぶたびに慎重になりスピードが落ち、成績が下降していった。
障害馬のあるあるだが、一度落馬すると飛越が怖くなり、成績が落ちる馬が多いみたいだ。
そんな時、伊藤先生がJRAから「競馬学校で生徒の馬術(障害)練習や、模擬レースなどで走らす馬が不足しているので、抹消する馬で丈夫な馬がいればお願いします!」と頼まれていた事から、ハナちゃんは競馬学校で第二の馬生を送る事となる。
2年間放牧に一度も出ず、23戦4勝(平地2勝、障害2勝)の成績を残して抹消となった。
競馬学校の騎手候補生は、学校の馬場や競馬場で卒業まで何回か模擬レースを行う。
馬は抽選で決まるのだが、ハナちゃんが競馬学校へ転出して以来、ほとんどの模擬レースで1着だった。
競馬開催時の昼休みなどに、騎手候補生たちがお客さんの前で模擬レースを披露するイベントがあり、テレビで見たことがあったが、ハナちゃんが大差勝ちしていた。
当時の生徒たちは皆、「模擬レースでのハナノエンは、誰が乗っても勝てる」だったそうで、その話を聞いた伊藤先生は「当たり前や!丈夫で競馬でもまだまだ走れる馬やったんやからな…」と言っていたのを思い出す。
ハナちゃんは数年間、たくさんの騎手候補生たちを騎手へと育て上げたが、その後も競馬学校で乗馬訓練用としてずっと大事にしてもらっていた。
僕は一度だけ中山競馬場出張の際に会いに行ったが、忘れているかと思われたチャックの上げ下げをすぐしてくれて、また号泣してしまった。

43年間の厩務員人生、担当馬好きな馬ランキング第1位、マチカネハナノエン。
もうハナちゃんを抜く馬は存在しない。