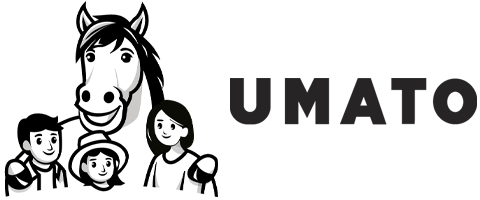(千葉県君津市)毎年7月22日前後
350年以上続く浜の大漁と岡の豊作を祈願する神事

人見神社は小糸川の河口、東京湾をのぞむ獅子山(人見山)の頂に鎮まり、古来より二総六妙見(上総の人見神社・久留里神社・横田神社、下総の千葉神社・印西妙見宮・飯高妙見宮)の一社として人々の篤い崇敬を受けてきました。
古く、日本武尊が相模から房総へむかう海上で嵐に遭ったとき、妃の弟橘姫命は自ら海中に身を投じて龍神の怒りを解き、暴風を鎮めたといいます。無事、上総へ渡った日本武尊は獅子山に登り、妃を追慕しつつ海路を「不斗(ふと)見そらし給う」たので「ふとみ」すなわち「人見(ひとみ)山」となったといわれています。


当日は朝の9時に宮司以下、役員代表者が神社にて祭典を斎行し、ついで若者たちが『おぶり』と呼ばれる竹の棒を境内に奉納します。
その人見神社では毎年7月22日前後に『神馬(おめし)奉納神事』が斎行されます。(2025年は7月20日)
旧17ヵ村の氏子や馬主、奉仕者らはすでに小糸川での神馬の水垢離、鳥居までの往復、奉納式などの儀を前日までに済ませていて、当日は朝の9時から宮司以下祭員と人見神社獅山会会長以下総代、役員、祭礼支配人以下役員、人見神社社家、そして十七ヶ村と呼ばれる君津富津の地域を治める神社の役員代表者が一同に集まり社殿の中へ入り、神の恵みに感謝し、また次の一年の平穏無事を祈念します。

9時30分~10時15分、山頂の大鳥居下の階段を、12本のおぼりを持った若者が駆け上がり、境内でのおぼり奉納を済ませます。
続いて神馬が神輿に続いて石段を上り、社殿へ参入、奉納神事となります。
馬を東回りに外へ誘導するのが口取りらの腕の見せ所で、さらに西回りに社殿を回らせ亀石につなぎます。東回りが上手くいくと、その年は豊作とされます。

神馬奉納に続いて手打式を行ない、馬主は神主から授かった御幣を鞍に結び、午前11時から大神輿へ神様の御霊を入れ、神輿が町内へ出発し、夕方まで市内をめぐります。途中午後の1時頃、神門(ごうど)自治会館前にて『神馬奉納』と『お浜出の儀式』をとりおこないます。
この350年以上続く伝統行事は1970年に君津市の市指定無形民俗文化財に選定されました。


神殿での儀式を終えた神馬は『御幣(ごへい)』を飾ります。また11時からは神輿渡御が夕方まで君津市内をめぐります。
人見神社
千葉県君津市人見892
アクセス
車◉立山自動車道 木更津南IC 「16号・富津岬・君津市街」方面下車15分
電車◉JR内房線 君津駅からタクシーで10分 青堀駅からタクシーで5分


人見山の山頂に鎮座する人見神社の高台からは君津市街一帯が見渡せ、さらには東京湾を挟んで神奈川県の三浦半島が見え『ちば眺望100景』に登録されています。
人見神社の起源
祭神を天之御中主命(あめのみなかぬしのかみ)・高皇産霊命(たかみむすびのかみ)・神皇産霊命(かみむすびのかみ)とし、この三柱の神々は「造化三神(ぞうかさんしん)」とも称えられ、高天原(たかまがはら)に最初に現れた崇高な神々であり、常に物事の中枢にあり、万物生成を司ります。
人見神社は奈良時代以前、孝徳天皇の代に日向国より勧請されました。また天慶三年(940年)、平忠常が上総介として赴任した折に武蔵国より北辰妙見の神霊を上総・下総各地に勧請した中の代表的な一社です。治承四年(1180年)、相模石橋山の合戦に敗れた源頼朝も、再起を期して内房の礒根伝いを舟で進軍の折、小糸川河口に着岸し当社に武運長久の祈願文を捧げたと伝えられています。天正19年(1591年)には徳川家康より良田五石の朱印の寄贈、元禄4年(1691年)には当地方の領主、小笠原彦太夫より大刀の献納、寛政9年(1797年)には小笠原兵庫と氏子らが浄財をもって春日造の社殿を造営しました。明治に入ると神仏分離の国策を受けて人見神社と称し郷社に列せられ、妙見菩薩は観音堂に祀ることになり、長い歴史の中で人見の杜は近郷近在の人々を見守り続けています。

取材後記…
山門から頂上までの石段の数はおよそ300段あり、約20分ほどで到着できます。健脚の方は夏の新緑に包まれた木々の中を歩くのはいかがでしょうか? 山頂にたどり着いた時の達成感が格別です。もちろん神社の中腹や山頂にも駐車場があります。暑い季節なので無理せず神事を参拝してください。 文/邦馬
取材協力・写真提供
人見神社
https://hitomi-jinja.jp/
0439-52-5008