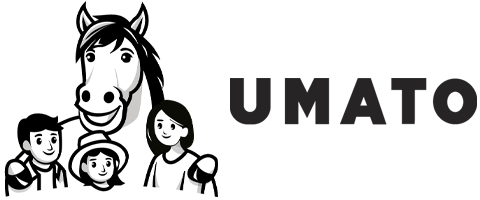(千葉県一宮町)毎年9月13日
1200年の歴史を誇る房総最古の浜降り神事

上総十二社(かずさじゅうにしゃ)祭りは玉前(たまさき)神社を中心に近隣の神社が寄り合い、毎年9月10日から14日にかけて斎行されます。13日が例大祭となっており、神輿の担ぎ手が裸に近いことから『上総裸祭り』とも呼ばれています。約2,500人が釣ヶ崎海岸の浜辺で「シオフミ」と呼ばれる海中を疾走する姿は圧巻の一言です。
その歴史は大同2年(807年)創始で、1200年以上の歴史と伝統を誇ります。


13日の例大祭を前にして10日にはお稚児さんの装束に身を包んだ子供達が町中を練り歩き、12日には県指定無形文化財「上総神楽」が奉納されます。
祭りの由来となっている物語は神々の出会いから始まります。悠久の昔、山の神である鵜茅葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)が海の神である玉依姫命(タマヨリヒメノミコト)を見初め、契りを結ばれました。そしてお生まれになった神武天皇をはじめとする神々は、海までつながっていると伝えられる井戸から水路を通って、九十九里浜まで流れていかれました。


13日の午前10時よりご本殿で例祭が斎行され、巫女たちが『浦安の舞』を奉納します。
その様は、龍の如しといわれ、元気な幼い神々は、海岸に着くやはしゃいで大暴れをなさいます。そこで、玉依姫をはじめとする御親族の神々は九十九里浜に幼い神々をおいさめに向かわれました。
このような伝承に因んで、現在では、毎年9月10日には、鵜茅葺不合命が鵜羽神社より神輿に乗って、玉前神社の玉依姫命を訪ね一年に一度の逢瀬の契りを結ぶという神事が執り行われます。続いて生まれた神々を鵜羽神社の井戸に流すという神事も行われます。


13日の午後、御幣を乗せた神馬(かんのんま)と神主(こうぬし)、命婦(みょうぶ)が神輿を先導します。
そして、13日には例大祭が古式ゆかしく厳かに行われます。神社本庁より献幣使(けんぺいし)をお迎えし、午前10時からご本殿で例大祭が行われます。
玉前雅楽会による奏楽(そうがく)のなか、おごそかに祭典が進められ、氏子の中学生が巫女となり、心を込めて「浦安の舞」を奉納します。


玉前神社からは2基の神輿列が釣ヶ崎祭典場へと向かいます。
午後1時からの神幸祭は、玉前神社を始め由縁の神々を奉じた9基のお神輿を千名余りの裸の男たちがそれぞれ担いでまちを巡り、釣ヶ崎祭典場へと向かいます。
伝承される物語にあるように九十九里浜の釣ヶ崎海岸では神々が集うという壮大な物語の神事が行われます。玉依姫命の一族の神々を祭る各神社より神輿を奉じて、神馬(かんのうま)が先導し、2500人余りの裸若衆たちが大海原を背に渚を疾走します。

再会を祝う神事の後、別れを惜しみつつ町を練り、午後7時半過ぎには玉前神社にお戻りになられ、待ち受ける大勢の観衆の掛け声と共にご本殿の周りを三周し、感動のクライマックスを迎えます。
このお祭りは房総半島に多く見られる浜降り神事の代表として広く知られ、壮大な儀礼をひと目見ようと、関東一円から大勢の人々が集い、平成15年3月に千葉県無形民俗文化財に指定されました。


9基の神輿が一堂に会し、年に1度の再会を祝い、威勢の良い掛け声の中、高々と掲げられます。
上総国一之宮 玉前神社
千葉県長生郡一宮町一宮3048
アクセス
車◉九十九里道路一宮ICから国道128号経由で約10分電車◉JR外房線 上総一之宮駅下車徒歩8分


真東を向いている玉前神社の一の鳥居。春分と秋分の日には、九十九里の海からのぼった太陽が鳥居を照らします。この日の、日の出の位置と玉前神社を結んだ延長線上には寒川神社、富士山山頂、七面山、竹生島、伊勢神宮の内宮が遷座したとされる元伊勢、皇大神宮、大山の大神山神社、出雲大社がならび、「御来光の道(レイライン)」と呼ばれています。
玉前神社の起源
一宮町は房総半島九十九里浜の最南端に位置し、一年を通して寒暑の差が少なく温暖な気候に恵まれた土地で、縄文弥生の頃から人々の営みがあったことが遺跡や貝塚などによって明らかにされています。歴史の古いこの一宮町の名称の由来となった玉前神社は祭神を玉依姫命(たまよりひめのみこと)とし、上総国にまつられる古社であり、平安時代にまとめられた『延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)』では名神大社(みょうじんたいしゃ)としてその名を列せられ、全国でも重きをおくべき神社として古くから朝廷・豪族・幕府の信仰を集め、上総国一之宮の格式を保ってまいりました。毎年九月十日から十三日に行われるご例祭には少なくとも千二百年の歴史があり、移りゆく時代に少しずつその形を変えながらも、古代からの深い意義を連綿と守り伝えてきたことを何よりの宝物として、この郷の人々と共に大切にしています。

取材後記…
玉前神社の境内にある『子宝・子授けイチョウ』。雄株・雌株・実生の子供イチョウの順に触れて、子宝に恵まれるようお祈りします。 子授けは縁結びと共に玉前神社の御神徳として広く知られ、子宝に恵まれたという様々な体験談が寄せられているそうです。文/邦馬
取材協力・写真提供
上総国一之宮 玉前神社
https://www.tamasaki.org
0475-42-2711