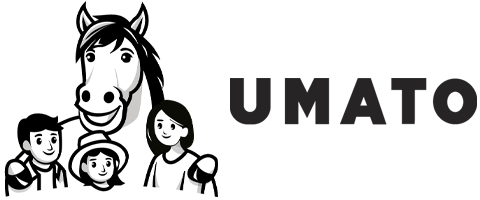今週の中京メインは金鯱賞。といえば、筆者が思い出すのは03〜05年にかけてこのレースを3連覇したタップダンスシチーである。
ツボにハマった時の強さは圧倒的なものがあった。以前にも当欄で紹介した03年ジャパンCでの9馬身差つけての逃げ切り。04年宝塚記念での2馬身差快勝。そして金鯱賞3連覇。ディープインパクトやイクイノックスのように、きらめくような華やかさがあるわけではないが、職人がしっかり仕事をして匠の凄みを見せつけるような重厚感が、この馬にはあった。
金鯱賞3勝目となった05年は出色の強さだった。前年有馬記念2着(1着ゼンノロブロイ)を最後に引退する予定だったが、一転して現役続行。すでに8歳となり、前年に引き続いて59キロを課せられたが、1000メートル通過61秒5のマイペースに持ち込んで悠々と逃げ切った。

「ペースが遅かった。意外に楽な競馬になったね」。佐藤哲三騎手(引退)は2馬身半差の完勝に会心の笑み。佐々木師は「衰えはないね。落ち着きが出たし、8歳の今年が一番、活躍できるかも」。残念ながら予言通りにはならず、この金鯱賞がキャリア最後の白星となったが、タップダンスシチーの底力を十分に見せつける一戦だった。
タップダンスシチーの取材はいつも楽しかった思い出がある。佐藤哲三騎手が馬の強さの説明をしたり、騎乗時の秘けつを解説するのだが、その発想が高度で新聞においての説明が難しい。必死に分かりやすく置き換えられる言葉を考え、どう例えたら読者に伝わるか、懸命に頭をめぐらせた。苦労はしたが、それもまた記者のだいご味だと今は思える。

佐々木晶三調教師の人間性から学ぶことも多かった。常に明るく、はきはきと話す。こちらが欲しがる言葉を読み取り、余すことなく期待に応えてくれる。時には、こちらが思う以上の反応が返ってきた。サービス精神が旺盛で、報道陣を信頼していることも伝わってきた。取材する側とされる側で相互に信頼し合っている感じがあった。
佐々木師の言葉に、はっとさせられたことがあった。04年、タップダンスシチーで宝塚記念を制した後のインタビュー。「強いレースだったが、当然の結果だと思っている。こんな気持ちになったのは3回目。シーキングザパールのシンザン記念(97年)、タップダンスシチーのジャパンC(03年)、そして今回だね」
シーキングザパール。98年モーリス・ド・ゲスト賞を勝ち、日本調教馬として初めて欧州GⅠを制して日本競馬史に名を刻んだ名馬だが、フランスGⅠを制した時は森秀行厩舎所属だった。シンザン記念を制した時は佐々木厩舎だったが、直後に転厩し、その後に世界へと飛翔した。
オーナーとの間にどんなことがあって転厩したのかは分からないが、自分の手元から離れていった馬のことは、あまり触れたくないだろう。まして、他の厩舎に移った後に歴史的大仕事をやってのけた馬だ。報道陣も佐々木師の前でシーキングザパールの話をすることはタブーというのが暗黙の了解だった気がする。
だが、そんなことは関係ないと言わんばかりに自らシーキングザパールの名を出してきた。筆者はそこに師の誇りを感じた。“シンザン記念を勝った時は、間違いなく自分の厩舎の馬だった”というプライドを感じさせた。「佐々木先生、随分と男前なこと言ったなあ」と思ったものだ。
この時のインタビューではもう1つ、重要なことに言及していた。「自分は佐藤哲三騎手を信頼している。02年の朝日チャレンジC(1着)で乗ってもらった時、呼吸がぴったりと合っていた。だからオーナーに“タップダンスシチーは引退まで佐藤哲三騎手でいかせてほしい”とお願いした」と明かした。
自分のひらめきを信じ、オーナーにそこまで言い切れる。そして結果、引退まで佐藤哲三騎手を乗せ切った。筆者は有言実行という言葉はあまり好きではないが、これはまさに有言実行だった。佐々木師、やっぱりオットコ前である。「佐々木師-佐藤哲三騎手の鉄壁コンビ」は佐々木師のひらめき、感性から生まれたものだった。
佐々木師は69歳。ということで定年引退が近い。ラムジェット(牡4)での大きな打ち上げ花火を期待したい。