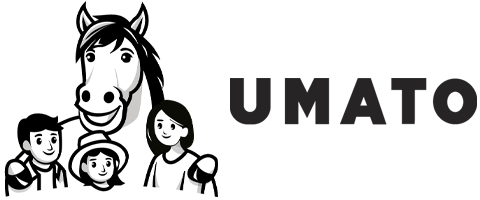使い古された言葉を持ち出して恐縮だが、「ダービーからダービーへ」という。
ダービーの翌週から新馬戦が始まり、1年後のダービーで世代の最強馬が決まる、という競馬独特のカレンダーのことだ。
ということで、今年もダービーが終わった。勝ったのは9番人気のダノンデサイル。横山典弘騎手のイン突破が見事に決まった。
このダノンデサイルをパドックで引き、表彰台で胸を張った厩務員に見覚えがあれば、その方は相当な競馬通だ。原口政也厩務員。当時の最多記録となる芝GⅠ7勝を挙げ、世紀末覇王と呼ばれたテイエムオペラオーを担当していた。
筆者はテイエムオペラオーの番記者だった。8戦8勝の完璧な成績をマークした00年は同馬が出走する週、ほぼ必ず栗東に出張し、岩元市三厩舎に張り付いた。
原口厩務員とはウマが合った。実は、番記者といっても関係者に突っ込んだ質問ばかりするわけではない。周囲をブラつきながら読者に、ふーんと思わせるネタを拾うのが役目だと思っていた。気がつけばそこにいる”空気”のような存在になりたかった。原口氏は、そんな筆者の思いを理解して、追い払うこともなく、そばにいることを許してくれた。
そんな”空気記者”に大命が下った。01年有馬記念。テイエムオペラオーの引退戦で、原口厩務員の日々に密着した連載をやれ、という上司の指示だった。原口氏も「いいですよ、協力します」と快諾してくれた。
競馬の世界に入るため過酷な減量をして試験に合格したこと。結婚したばかりの奥様とのなれそめなど、他紙にはないエピソードを次々と提供してくれた。
決戦の地、中山に移動した12月22日。原口氏は取って置きのネタをくれた。移動の馬運車の車中で食べた奥様手作りのお弁当に手紙が添えてあったという。ここまでオペラオーとともに奮闘した主人をねぎらい、悔いのないラストランにしてほしいという内容だった。

ダメを承知で聞いてみた。「あのー、原口君。このお手紙、新聞に載せてもいいかな」。まあ、8割方、無理と思っていた。自分が同じ立場だったら「勘弁してくださいよ」と断るだろう。ところが返事は…「いいですよ」。翌日、奥様からの愛にあふれた手紙がスポニチに掲載された。
まいった。一生、原口君には頭が上がらないと感じた。この時以降、原口家にはお中元とお歳暮を欠かすことなく贈っている。あの時の心からの感謝の気持ちを忘れたくないからだ。
テイエムオペラオーは皐月賞を制したが、ダービーは3着(1着アドマイヤベガ)だった。四半世紀ぶりに忘れ物を取り返したようなものだが、原口氏の喜び方は普通の重賞を勝った時と何ら変わらないものだった。そういう冷静なハートの持ち主だから、除外明けのダービー制覇という、とてつもないことをやってのけたのだろう。改めて、素晴らしいホースマンだと感じた。