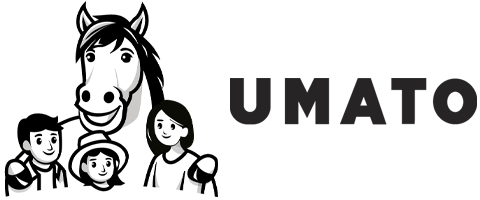98年11月1日、東京競馬場。天皇賞・秋を終えたばかりの検量室前は騒然としていた。4コーナーで故障したサイレンススズカ。担当記者たちは、史上最強かといわれた名馬が今、どんな状況になっているのか、誰も分かっていなかった。
武豊騎手が戻ってきた。筆者にとって衝撃過ぎて記憶が飛んでおり、武豊騎手が歩いて戻ってきたのか、関係車両に乗って戻ってきたのか、記憶にない。とにかく横に張り付き、全ての言葉を聞き逃すまいとペンを手に取った。

「突然でした。デビュー以来、一番の出来だった。自信を持って臨んだ。レースでも理想的なペースを踏めたのに…」。ペンを持つ手が震えた。こんなショッキングなことを直接体験したばかりなのに、しっかりと言葉を絞り出す武豊騎手は心底凄いと思った。
報道陣から質問の声が上がった。質問の詳細な内容は失念したが、武豊騎手は怒気を含んでこう答えた。「原因は分からないのではなく、ない」
武豊騎手を囲む大きな輪が解け、スポーツ紙記者数人だけが武豊騎手と話す状況となった。「もう競走馬としては無理だと覚悟している。でも、せめて無事でいてほしい」。この時点で検量室前に“最悪の事態”となった情報は届いていなかった。
検量室前で情報を待つ。そこに加茂厩務員がうなだれながら戻ってくるのが見えた。筆者は全てを察した。恐らく診療所でサイレンススズカの最期を見届け、主のいなくなった馬房へと戻るのだろう。
加茂さんのそばにいてあげなきゃ。とっさにそう思った。
この日、サイレンススズカの執筆担当だった筆者。本来なら橋田満師の戻りを待ち、言葉を聞かなければいけない。だが、業務よりもはるかに大事なことがある気がした。橋田師の取材を先輩記者に頼み、加茂厩務員の元へと駆けだした。先輩記者も状況を察し「行ってこい」と言ってくれた。
泣きじゃくりながら地下道を歩く加茂厩務員の横で、どんな声をかけていいのか分からなかった。加茂厩務員が、これまで出したことのないような大きく、はっきりとした声で、こう言った。「1人で帰るなんてダメなんだよ。2人で帰らなきゃダメなんだ」。涙が出た。手にはサイレンススズカの“形見”となった馬具があった。こんな残酷なことがあっていいのか、と思った。
厩舎へと戻った。がらんとした馬房を目の当たりにして、この世にもうサイレンススズカがいないんだという事実を突きつけられた。
少し、気持ちが落ち着いた加茂厩務員が、こう話した。「膝が反り返っていたよ。とても見ていられなかった。故障も競走馬の宿命だけど…種牡馬になることが本当に楽しみだったのに…」。そう言いながら、サイレンススズカのいない馬房の前で、黙々と馬具を片付けた。
「加茂さん、元気出して。栗東に行ったら、また顔を出します」。何の慰めにもならない言葉をかけて、筆者は馬房を後にした。
地下道を再び、歩いて戻る。最終レースを終えた馬たちが厩務員とともに馬房へと戻っていくところとすれ違った。何度も見た風景だが、この風景がどんなにありがたく、どんなに崇高なものかを実感した。
サイレンススズカ。天皇賞・秋を迎えるたび、筆者は加茂厩務員と2人で泣きながら馬房へと戻った、あの地下道を思い出す。