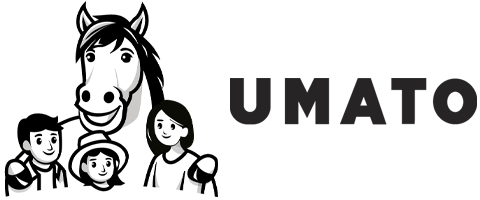(愛知県 一宮市)毎年4月1日~3日
別名「馬まつり」とも称される桃の節句にちなんだ厄払いの祭り

真清田(ますみだ)神社は尾張の国で最初に参拝する「一の宮」であり、一宮市の名前もそのことから付けられました。この地がいかに真清田神社を中心として発達したかがわかります。御祭神を天火明命(あめのほあかりのみこと)とし、仕事運や出世運、開運厄除、子孫繁栄にご利益があるとされています。
真清田神社の例祭である桃花祭(とうかさい)は、江戸時代までは、3月の桃の節句に行われていましたが、明治43年から太陽暦の4月3日に行われています。

古き昔、真清田神社の周りは桃の木が群生し、この地は「青桃丘(せいとうきゅう)」と呼ばれていました。霊力があると信じられているこの桃の枝をもって身のけがれを祓い、当時神社の近くを流れていた木曽川にこの枝を流して除災招福を祈ったのがこの祭りの始まりとされます。
今日では神前に備える供物に桃の小枝を添え、この神事に奉仕する者全てが冠に桃の小枝をつけています。

桃花祭は別名を「馬まつり」とも称され、馬上に御幣(ごへい)、人形をのせた「馬の塔(うまのとう)」が、神輿渡御に供して勇壮、華麗に練り出されます。
市内では、4月1日の朝に献灯が飾られ、1日には神前で和歌を被講する短冊祭が斎行されます。また2日には歩射神事が斎行され、その年の豊凶を占います。
3日は午前中に社殿で神事が斎行され、11時半からは流鏑馬が奉納されます。そして昼の12時に女性の騎馬武者が神幸行列を先導し、一宮市の街中を通り、冨士三社境内にある御旅所へと向かいます。ここで御旅所祭を斎行したのち、神幸行列はふたたび市内の商店街をめぐり、真清田神社へと戻ります。
一宮市の代表的なお祭りである桃花祭は市内はもとより県外からも多くの観客が集まり、一宮に春の訪れを知らせます。


4月2日には歩射神事が斎行されます。また3日の午前11時30分からは境内にて流鏑馬が奉納されます。


真清田神社
愛知県一宮市真清田1丁目2-1
アクセス
車◉名神高速「尾張一宮」I.Cより約20分
名古屋高速一宮線「一宮東」出口より約10分
東海北陸自動車道「一宮西」I.Cから約10分、
「一宮木曽川」I.Cから約15分
電車◉JR東海道本線 尾張一宮駅 名古屋鉄道 一宮駅下車徒歩8分

真清田神社の起源
真清田神社は、平安時代、国家から国幣の名神大社と認められ、神階は正四位上に叙せられ、尾張国の一宮として、国司を始め人々の崇敬を集めました。鎌倉時代には、順徳天皇は当社を崇敬され、多数の舞楽面をご奉納になりました。その舞楽面は、現在も、重要文化財として保存されています。江戸時代には、徳川幕府は神領として、朱印領333石を奉りました。また、尾張藩主徳川義直は、寛永8年(1631年)当社の大修理を行う等、崇敬を篤くしました。明治18年には国幣小社、大正3年に国幣中社に列し、皇室国家から厚待遇を受けました。戦後は、一宮市の氏神として、一宮市民はもちろん、尾張全体及び近隣からも厚い信仰心を寄せられ今日に至っています。
取材後記…
真清田神社では毎年10月15日に駒牽(こまひき)神事が斎行されます。この駒牽神事は桃花祭に奉納する馬の足並みや馬体の良否を検閲するための神事です。当日は約15頭ほどの馬が神社内を駆け、境内は大いににぎわいます。文/邦馬

取材協力・写真提供
真清田神社
http://www.masumida.or.jp/
0586-73-5196