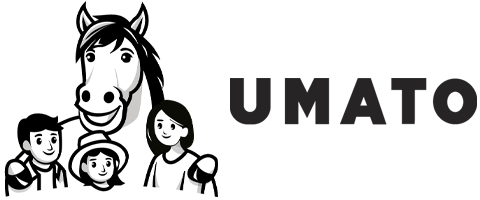(福島県いわき市)毎年9月第2土曜日
別名『生姜祭り』とも呼ばれる鎌倉時代から続く伝統行事

古くから飯野八幡宮の例祭は8月14、15日に斎行されていましたが、明治40年より太陽暦の9月14・15日に改められました。
祭礼は、9月1日の祭始祭から始まり、円座的祭(令和7年は9日)、潮垢離神事(令和7年は13日)と続きます。潮垢離神事は藤間の浦(舞子浜ビーチ付近)で斎行されます。この神事では、例祭を迎えるにあたり、宮司を始め、流鏑馬騎士、総代および流鏑馬用具、神馬が藤間浦において心身ともに清められます。その歴史は飯野家文書「八幡宮縁起」の中に建暦元年(1211年)「御濱出」と記されており、約800余年の間、連綿と継承されてきた神事です。
そして流鏑馬神事は9月第2土曜日の午後に斎行されます。騎士は狩りの装束で笠、むかばき、箙を着け、弓を持ちます。笠は五色の紙垂で飾られ、馬の背には蒔絵の和鞍が置かれます。また、馬の四脚は、藤間の海岸から角樽で汲み上げてきた潮水で清められます。
神前で御祓いをうけたあと、神域を一巡して一の鳥居の前で礼射式を行い、ついで馬場へと向かいます。馬場では空駆け、生姜撒き、扇子撒き、的矢の順で行われます。その歴史は飯野八幡宮所蔵の古文書によれば、貞和2年(1346年)にこの神事が行われた事が記されています。


例大祭の前日にされる『潮垢離神事』と『浦安舞』の奉納。『浦安舞』は例大祭でも午前10時半あたりに行われます。

流鏑馬の回数は奇数とされており、状況により、7、9、11回ほど行われます。神社前の市道は元々流鏑馬の馬場であり、現在もここで古式勇壮な流鏑馬神事が行われます。
翌日の第2日曜日は古式大祭とし、神輿渡御と八十八膳献饌が行われます。神輿は稲荷台にある御旅所まで渡御した後、神社に遷御すると直ちに、八十八膳の献饌が始まります。この八十八膳献饌は古くから連綿と受け継がれてきたもので、県の重要無形民俗文化財に指定されています。
また飯野八幡宮の祭礼は別名『生姜祭り』ともいわれています。言い伝えによれば、源頼義公が前九年の役に出征のおり、ひどい暑気あたりにかかられ、地方の農民が献じた生姜を食され、その病を治癒された、と言われています。生姜は漢方で健胃薬とされており、親の根生姜も子の新生姜も育つとの縁起で、参拝者はこの生姜を求め、福を受けるという風習になったと言われています。


的は杉板七枚組で方二尺五寸の大きさで馬場の3ヵ所に立てます。

飯野八幡宮
福島県いわき市平八幡小路84
アクセス
車◉常磐自動車道いわき中央ICから約15分
電車◉JR常磐線・磐越東線 いわき駅から車約6分


飯野八幡宮では多くの指定文化財を保有しています。国指定の重要文化財だけでも、『本殿』『大薙刀』『飯野家文書』『楼門』『神楽殿』『唐門』『仮殿』『宝蔵』『若宮八幡神社』と9つを数えます。
飯野八幡宮の起源
御祭神は品陀別命(ほんだわけのみこと)、息長帯姫命 (おきながたらしひめのみこと)、比賣神 (ひめがみ)。
社伝によれば、康平6年(1063年)源頼義が奥州合戦(前九年の役)出征の時、京都石清水八幡宮を必勝祈願のため勧請したとあります。しかし、文治2年(1186年)関東御領好嶋荘の総社として、源頼朝の命により本社石清水より御正躰を奉じて、赤目崎見物岡(現いわき駅北の高台)へ祭祀したとの別伝も記録に見られます。建永元年(1247年)時の執権北條時頼は、幕府政所執事伊賀光宗(宮司飯野家の祖)を好嶋荘の預所に任命しました。以後代々預所職と神主職を兼ね、現宮司、飯野光世にいたります。

取材後記…
飯野八幡宮では国指定の文化財の他に、県指定、市指定の文化財も数多くあります。中には馬にまつわるものもあり県指定の重要有形民俗文化財『絵馬 引馬図』は狩野派の画人の作で、高さ83cm、横幅114cmあり、寛永20年(1643年)頃に磐城平藩主内藤氏が奉納したと言われています。文/邦馬
取材協力・写真提供
飯野八幡宮
http://www.noteplan.net/8man/index.html
0246-21-2444
(一社)いわき観光まちづくりビューロー
https://kankou-iwaki.or.jp
0246-44-6545