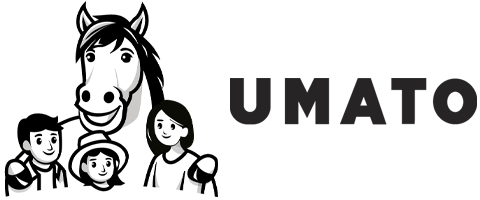今週のGⅠは桜花賞。毎年のように名勝負が繰り広げられる一戦だが、筆者の印象に強く残るのは14年の優勝馬ハープスターだ。
4角最後方から直線だけで全馬をごぼう抜き。上がり3ハロンは驚異の32秒9。勝ちタイムは1分33秒3は桜花賞タイレコード(当時)。牝馬クラシックも凄い時代に突入したものだと素直に驚嘆した。
当時、筆者は中央競馬担当デスクだった。桜花賞ウイーク前。栗東から阪神へと出張して桜花賞を伝える予定の女性記者が相談に来た。「もしハープスターが勝った時、事前にどんな取材をしておけばハープスターの強さが伝わる記事が書けますか?」
その女性記者は新潟2歳Sやチューリップ賞を見て、すっかりハープスターの末脚に魅了されていた。念願の競馬記者となって初めて出会った魅力的な牝馬。ハープスターの凄さを全国の競馬ファンに知ってもらいたいと意気込んでいた。

後輩のやる気には全力で応えたい。筆者も松田博資(ひろよし)調教師への取材の仕方やハープスターの血統背景など、基礎知識を伝えた。
そして、こう補足した。分からないことは素直に、正直に松田博資師に聞くべき。師は「そんなことも知らないのか」と言う方ではない。
もうひとつ。松田博資師はハープスターの母の母ベガも管理して93年桜花賞を勝った。このベガから学んだこと、ハープスターにつながる何かがあるのか。このあたりがキーになるのではないか、と伝えた。
ハープスターがゴールに飛び込んでから数時間。阪神の女性記者から原稿が届いた。素晴らしかった。中間、松田博資師に密着し、分からないことを率直に聞き、メモを取りまくったのであろう。そういう風景が鮮明に脳裏に浮かぶ原稿だった。
“牝馬のマツパク”と呼ばれる。なぜ、こんなにも牝馬が強いのか――。「ウチは牝馬も牡馬も関係なく、みんな鍛えるからな」。いい言葉を指揮官から引き出していた。
さらに、松田博資厩舎にいる馬は牡牝関係なく、レース翌日を除いて必ず馬場入りさせることを紹介(このことを原稿にすることも実はそう簡単ではない)。「これは昔のやり方なんだ。昔は休みなんてなかった。それに、乗らないと本当の馬の状態なんて分からない」という言葉を指揮官から引き出した。
最新の血統と、古き良き管理術がマッチしての戴冠。こんな見方、ライバル紙のどこも掲載していない。しびれるような原稿だ。
ベガが鍵になる――。その答えもこちらの想像以上のものがあった。
「ベガの血を引く馬。やはり感動したね」。師は素直な思いを吐露した。「ベガは初めて海外を意識させてくれた馬。こういう馬が海外に行くんだと思わせてくれた馬だった」。ベガで海外に行きたかったとは…。筆者は師から聞いたことがなかったし、想像もしていなかった。女性記者は、あっという間に松田博資師に心を開かせ、取っておきの話をつかんできた。大したものだ。
この桜花賞は筆者自身もデスクとして成長できたように思う。的確な指示、ヒントを与えれば、後輩記者はきっちり期待に応えてくれる。いや、むしろ期待以上の収穫を手にしてくれた。自分の経験を後進に伝え、さらに大きく花開かせることの面白さを味わった、忘れられない桜花賞だった。