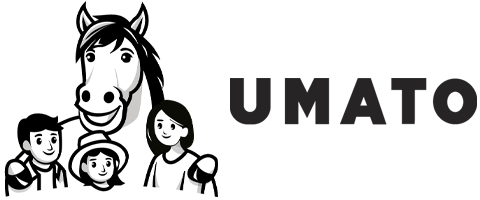競馬を始めた当初から、ずっと疑問に思っていたこと。今回は、それの解決に挑む。テーマは…「中山競馬場と東京競馬場。同じ首都圏にある競馬場なのに全く個性が違うのはなぜ?」
「個性」とはなんぞや。左回りと右回りの違いとか、坂のあるなしとか、そういうことではない。もっと“雰囲気”的なものである。
あくまでも個人的な受け止めだが、東京競馬場は全体的にスマート。一方で中山競馬場は雑多でカオスな感じがする。

東京の代表的なレースはダービー。競馬最大の目的である“強い馬を決める”正統派だ。中山の代表は有馬記念。小回りで坂もあるトリッキーなコースで行う非根幹距離の一番。師走という時期も相まって、いかにも“ギャンブル”という独特のにおいを醸し出す。
もちろん、どちらがいいとか悪いとか、そういうことではない。ただ、「どちらが好き」という話はできる。
筆者は…中山が好きだ。中山競馬場も広くて大きいが、東京と比べると、どこか、せせこましい。重賞のパドックでは、どうしても隣の人と肩が触れ合う。でも、それがいい。
競馬場の周囲の環境も最高だ。木下街道には昔の雰囲気が十分に残っている。東中山駅や下総中山駅に向かう道にも昭和の頃の雰囲気がまだ存在する。
もう35年くらい前だが、そのおけら街道を歩いている時、「昔はこのあたりで競馬場帰りの客を狙ったバクチが開帳されていて、やられる人がいたもんだ。いかがわしい写真も売っていた」と、その道のベテラン(というか隣を歩いていたおじさん)から聞いた。今はもちろん、そんなバクチは行われていないが、競馬と違法バクチのダブルでやられたオヤジたちは確実にいたのだろう。目に浮かぶ。
そんな中山の猥雑さ(褒めている)は、どこから来るのか。社にある『中山競馬場70年史』(平成10年、中山競馬場発行)にヒントを求めてみた。
下総地区の競馬場といえば元々は松戸だった。1905年(明38)あたり。松戸駅東口すぐの高台、今は松戸中央公園や聖徳大学があるところに1周半マイルの小さな馬場をこしらえ、草競馬を行ったそうだ。
その後、政府の閣令で1周1マイルの馬場が必須となり、1907年(明40)に拡張工事が行われた。だが、このコースが凄かった。
競馬場のある高台を普通に1周しただけでは1マイルに届かない。そこで2コーナー付近に不自然な湾曲(通称・天狗の鼻)を作って、何とか1マイルを確保したのだという。まるでサーキットのようなコースレイアウト。当然ながら落馬事故が多発した。
何だろう、このスリルとバクチ感。師走競馬の総本山・中山の前身にふさわしい競馬場と言えないか。
しかし、松戸競馬倶楽部はラッキーだった。競馬場の土地に陸軍工兵学校を創設させてくれと当局が打診してくるのである。1918年(大7)頃のこと。倶楽部は小躍りして?欠陥競馬場の土地を譲り、中山の地に移転するのだ。ちなみに現在の競馬場より、やや南側にあり、設備はかなり貧弱だったそうだ。

「移転した」と書いたが、実は話はそう簡単ではない。詳細は省くが、松戸から名前を変えた中山競馬倶楽部には内紛が続出する。
中山での開催はたびたび中断され、業を煮やしたある一派は東葛飾郡行徳町(現市川市)に新たに競馬場を計画。中山からの移転をもくろみ、9割方、完成させたという。
ところが1923年(大12)に発生した関東大震災により“行徳競馬場”は壊滅的な打撃を受け、計画は頓挫。この競馬場が無傷だったら、中山、行徳の両競馬場の運命は大きく変わっていただろう。
その後、肥田金一郎というカリスマが現れ、新・中山競馬場を計画し、地主と粘り強く交渉。当局も「ゴタゴタしていないで、設備を整えて開催しないと許可を取り消すよ」という通牒を出し、ようやくバラバラの倶楽部がまとまるのだ。
ぶつかり合うような強烈な個性は団結すれば強い。そこから新・中山競馬場は数々のアイデアを実現させ、スケールで上回る東京競馬場と互角に渡り合っていく。
中山大障害を構想してまずは成功を収めた。国営競馬を経て、日本中央競馬会の一競馬場となってからも、野球のオールスターから着想した「中山グランプリ」を開催して、これまた大成功。こちらは翌年から「有馬記念」と名を変え、今も中山を代表する大一番として定着している。
いかがだろう。松戸にヘンテコ競馬場(失礼!)を作ってスタートし、内紛に内紛を重ねた末、ギャンブラーの期待に応えようとアイデア勝負で人気を集めた競馬場。それが中山。その時代、その時代の人々の熱意、苦労が集積して、中山にしか出せないムードを今も醸し出しているとしか思えない。
素晴らしき関東の鉄火場。この雰囲気をいつまでも残してもらいたいと思っているのは筆者だけではないはずだ。