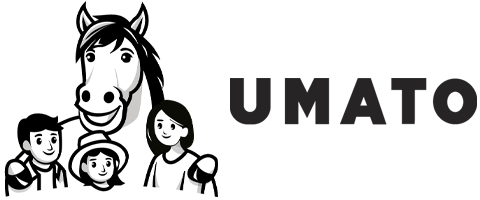パリ五輪が終わった。筆者の心に最も残ったシーンは柔道女子52キロ級2回戦で敗れ、号泣した阿部詩の姿だった。
会場内に響き渡る声で慟哭した。このことについては、さまざまな声が国内外から上がったが、自分が心をつかまれたのは、号泣という行為の是非ではない。究極の領域まで努力を重ねた選手が、意に反した結果が出た時、ここまで泣けるのだという単純な驚きだった。
一般的に人は挫折した時、果たしてあのレベルまで泣けるか。阿部選手は泣ける。そこまで努力し、自分を追い込んだのだ。そのことがはっきりと見えたから、心に突き刺さった。阿部詩という人のエネルギーに凄みを感じた。
幸い、28年ロス五輪でのリベンジを期しているとのこと。ぜひ、逆襲してほしい。同じ泣くなら笑顔で泣くシーンを見たい。
競馬における「涙」で最も印象深いのは11年ジャパンC。ブエナビスタで制した松田博資調教師の涙だった。
涙、どころではない。号泣だった。「おおお」と声を上げて泣いた。どちらかと言えばキリッとした親分肌で、涙とは縁遠い人だと思っていたが、とんでもない思い違いだった。
話は前年にさかのぼる。10年ジャパンC。クリストフ・スミヨンを鞍上に迎え、天皇賞・秋を制したブエナビスタはGⅠ連勝を狙って大一番に駒を進めた。
直線、ブエナビスタは豪快に抜け出して圧勝したかに見えた。スミヨンは派手なウイニングランまでした。しかし、喜びは暗転する。24分の審議の末、内斜行で2着へと降着。ローズキングダムが1着へと繰り上がった。
松田博師はぶ然とした表情で何度も首をひねった。「降着自体は裁決が決めることだから。オレはスミヨンが悪いとは思っていないが…」。わずかに目元がうるみかけたのが、その後だった。「馬も勝ったはずなのに(表彰式などが)何もなくて、なんでだろうと思っているんじゃないか」。
ずれた歯車はなかなか元には戻らない。ブエナビスタは白星から遠ざかった。連覇を目指した11年天皇賞・秋は4着。リベンジ舞台となるはずの11年ジャパンCでは国内戦で初めて1番人気から滑り落ち、2番人気に甘んじた。
ここでブエナビスタが奮起する。直線で前後左右を馬に囲まれたが、トーセンジョーダンの外にできた1頭分のスペースを岩田康誠騎手は見逃さなかった。残り50mで先頭。1年越しのリベンジが成ると、岩田騎手は右手の拳を握りしめ、何かを叫んだ。
松田博師は記者会見で、前年の降着に話が及ぶと、人目をはばかることなく声を上げて泣いた。「去年はスミヨンに悪いことをした。本当に悪かった。今年、勝てて良かった」。
短期免許で来日した外国人騎手とのコンビ。そこにはビジネス的要素を感じてきたが、松田博師にとってはそうではなかった。管理馬に乗せる以上、どの騎手も大事な息子のような存在だったのだろう。スミヨンとて例外ではない。それが外国人かどうかは問題ではないのだ。
松田博師の涙を見て、大陸的な器の大きさを感じたことを昨日のことのように思い出す。