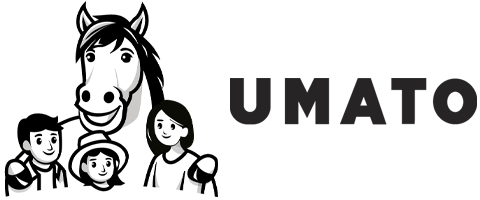今年も凱旋門賞デーが近づいてきた。実は筆者、「いつか凱旋門賞を日本馬が勝つ日が来るので、御社の競馬記者として、その記念すべき原稿を書きたい」と面接でアピールして、スポーツ紙の記者となった。残念ながら記者として優勝を見届けることはなかったが、何度か現地でレースを取材する幸運には恵まれた。今回は最も記憶に残る名馬を紹介しつつ、凱旋門賞とは何かを自分なりに考察したい。
99年エルコンドルパサー。筆者が初めて記者として現地取材した忘れられない馬だ。

GⅠサンクルー大賞、前哨戦の1つ・フォワ賞を快勝し、期待十分に本番へ。蛯名正義騎手(現調教師)を背に、勝つ寸前まで行ったが、地元フランスのダービー馬モンジューの前にわずかに敗れた。
エルコンドルパサーを通して学んだことが2つある。まずは「長期遠征は確実に勝利に近づく方法の1つである」こと。
同馬は3歳時にジャパンCを勝った後、フランスに腰を据えた長期遠征を敢行した。渡邊隆オーナーの「スポット参戦では凱旋門賞のような大舞台を勝つことは難しい。長期滞在で“現地の馬”になることが優勝への近道だ」という大胆な発想によるものだ。
効果は絶大だった。筆者はエルコンドルパサーが凱旋門賞前に出走した3戦、全てを現地で見届けたが、レースを迎えるたびにトモ(後肢)がグッと成長し、体全体が重厚になっていくのが分かった。
日本と異なる食事、水、時に日本ではあり得ない重さとなる調教場のコンディション。それらにより、エルコンドルパサーはどんどん欧州仕様へと変わっていった。二ノ宮師も、帯同した佐々木幸二調教助手も「日本の頃とは走り方が全く変わった」と話した。ロンシャン向きの馬になっていったのである。
それから「ノウハウを伝えていくことの重要性」だ。
エルコンドルパサーはタイキシャトルと同じ、トニー・クラウト厩舎の馬房を借りていた。きっかけは(タイキシャトルの)藤沢和雄調教師ではなく、渡邊オーナーとクラウト師の個人的な関係のようだが、それでも前年に滞在した藤沢和厩舎からエルコンドルパサーの二ノ宮厩舎への情報伝達が行われたであろうことは想像に難くない。クラウト厩舎側にも「日本馬をどう迎えるか」というノウハウが生まれていたはずだ。
タイキシャトルの遠征時に活躍した多田信尊マネジャーが、エルコンドルパサーにおいても起用されたことも、ある意味、ノウハウの受け渡しだった。多田氏の起用により、交渉事は全てスムーズに運んだ。

あれから時代は流れた。前者の「現地の馬になれ」は、のちに橋田満厩舎の牝馬ディアドラが実行し、19年に英GⅠナッソーS制覇という収穫を得た。とはいえ、なかなか欧州に腰を据える馬は出てこない。資金面の問題が大きいのだろう。ただ、今の時代でも実行すれば相当な成果を上げられると思われる。
後者の「ノウハウの伝達」は今も最重要の要素である。二ノ宮厩舎はエルコンドルパサーの後もナカヤマフェスタで10年2着。エルコンドルパサーでの経験が生きたことは間違いない。
その後も美浦、栗東の調教師、スタッフだけでなく、社台グループをはじめとした牧場関係者も着々とノウハウを獲得。後進へと引き継いできた。現地に日本人調教師も開業し、フランスに武者修行に訪れる若手騎手も増えた。今回、調教師としてアロヒアリイを送り出す田中博康調教師も騎手時代にフランスに長期滞在した1人である。
ノウハウがあれば基本的に慌てることはない。異国の地で慌てないのは重要なことである。滞在からレース出走まで、全てが日本にいる時と同様に運べば、人馬とも力を出し切れる。その中にはゴールを先頭で駆け抜ける猛者もいるだろう。
10年ヴィクトワールピサを凱旋門賞(7着)に送り出した角居勝彦元調教師が現地でこんな話をしてくれた。「もっとチーム・ジャパンになればいい。強い馬だけでなく、ロンシャンの馬場にフィットしそうな馬、遠征に強い馬をピックアップして複数頭、厩舎の垣根を越えてフランスに送り込む。そうすれば調教のバリエーションが増えて、どの馬も力を出し切れる態勢が整う。その上で本番を迎えれば、どれかが突き抜ける可能性が生まれる。角居厩舎でなくてもいい。誰かが勝てばいいと僕は思う。多くの人が“チーム・ジャパン”の発想を持てば、いつかは凱旋門賞を勝てると思いますよ」
今や、賞金額で上回り、格の上でも肩を並べるレースが世界中にあるのに、日本人ホースマンは、なぜ凱旋門賞を勝ちたいのか。それは凱旋門賞が、先人の発見や経験を必ず引き継ぐ必要があり、そこに自らの発想、努力、周囲の積極的な協力も加えて初めて勝てるという壮大なレースだからだ。
単発ではほぼ無理。考察、準備、協力、実行。将棋のように先を見据えながら、日本人ホースマン全員で相手を追い詰めていくイメージ。言葉だけ聞くと競馬でないようだが、だからこそ、これこそが究極の競馬。面白くないはずがない。
今年はどんなドラマが見られるのか。日本人ホースマンたちの戦いぶりを目に焼き付けたい。